屋根の修理やリフォームを検討する際に、少しでも修理費用を抑えたいと思う方は多いでしょう。 費用を抑えるためには、工事費を安くする方法に加え、補助金を活用するという方法があります。 実は、屋根修理でも補助金や助成金の対象になることがあります。 活用することができる助成金・補助金は大きく分けると2つあり、修理内容がどちらかに該当すれば助成金、補助金を受けられる可能性があります。 こちらの記事では、屋根修理に関わる補助金について詳しく解説をしていきます。 これから屋根修理を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
省エネ目的のリフォーム

まずは、省エネを目的としたリフォームで補助金が出る可能性があります。
省エネリフォームは環境に優しく、消費するエネルギーを少なくすることを目的とした住宅改修工事を指しています。
住宅の省エネ化を促進するリフォームであれば補助金や助成金が利用でき、以下のような工事の場合に利用が可能です。
- 太陽光パネルの設置
- LED照明の設置
- アスベストを含んだ屋根材の撤去
- 住宅の断熱・遮熱化
これらの工事は、電力などの使用エネルギーを削減できる効果が期待できることから、省エネリフォームとして考えられます。
耐震化目的のリフォーム
日本は地震大国であり、毎年のように大きな地震が心配されています。
そのため、建物の耐震化は非常に重要な課題であるため、耐震目的のリフォームでも補助金が出る可能性があります。
対象となる屋根の修理は下記のような内容です。
- 屋根の軽量化
- 屋根補修
- 金物補強
- 仮設足場の設置
特に耐震化で最も重要なことが、屋根の軽量化とされています。
屋根の修理やリフォームには大きな金額がかかりますが、自治体が補助をしてくれる可能性があるため、上手に活用していきましょう。
耐震化リフォームでは、改修工事の他に診断・補強工事の設計・工事監理にかかる費用も助成金が利用できます。
地震はいつ来てもおかしくないため、耐震性に不安のある方は、なるべく早急に工事を依頼するとよいでしょう。
屋根修理の代表的な助成金・補助金制度

屋根修理に使える助成金・補助金は自治体によって異なりますが、ここからは代表的な制度を1つずつ紹介していきます。
長期優良化リフォーム推進事業制度
こちらは、国が実施している補助金制度で、既存住宅(中古住宅)において、劣化対策や耐震性、省エネルギー対策など、住宅の性能を一定の基準まで向上させるリフォーム工事費用に対し、国が補助金を交付する制度です。
この制度では、屋根の軽量化や屋根補修といったリフォームが補助金支給の対象となっています。
限度額は1戸あたり100万円となっていますが、さらに増額されるケースもあるようです。複雑な点も多いため、もし利用を検討している方は、問い合わせをしてみましょう。
ただし、申請には締め切りがあるため、詳しくはホームページ等を確認してみましょう。
省エネ改修補助事業
こちらは各自治体によって定められている制度で、断熱改修による省エネ基準の向上を推進する目的のものです。
特に築年数が古くなった住宅に対して断熱工事をした時に支給されます。
支給額は自治体によって異なりますが、上限が20~30万円ほどに設定されているケースが多いです。
耐震診断・改修等補助制度
地震による耐震性の向上を目的とした制度で、特に旧耐震基準で建てられた住宅のリフォームに対して適用される補助です。
耐震工事だけでなく耐震診断にかかる費用なども補助もしてくれるため、住宅の耐震性が気になる方も利用することができます。
支給額の上限は20万円ほどが相場となります。
屋根の修理で助成金・補助金を受ける条件は?

さて、助成金が利用できる工事内容を解説してきましたが、国や自治体の補助金・助成金を利用する時には、さらに細かな条件を満たす必要があります。 単に省エネの工事をすれば良いというわけではないため、補助金をしっかりと受け取るためにも、条件について解説をしていきます。
省エネ・耐震性向上に一定の効果があると認められること
リフォームや修理では、屋根や外壁の悪い部分を修理するため、省エネや耐震性を目的としていなくても、多少の効果を得ることができます。
しかしその工事を、省エネ、耐震性と言い張ってしまうのは無理があります。
そのため、各自治体の役所ごとに条件が示されています。
条件に当てはまった工事や工法でなければ、助成金・補助金を受けることができないため、ホームページや問い合わせをして条件をしっかりと確認しておきましょう。
工事前に申請していること
助成金や補助金を受けるためには、工事後に後付けで申請をしても受け取ることができません。
工事前に必要書類や、修理箇所や劣化した箇所の写真を撮って、自治体に申請を行います。
工事前の状態で証明を行うことで、行われた工事が省エネ・耐震力向上の目的に沿っているのかを自治体が判断できます。
そのため、修理業者は補助金や助成金に詳しい業者を選ぶようにしましょう。
中には指定を受けている可能性もあるため、業者を探すときに補助金を使用したい旨を伝えるとスムーズに進みます。
税金の未納・滞納がないこと
これらの補助金や助成金は、税金を元手に自治体から支払われます。
そのため、申請者に税金の未納や滞納がないことが最低限の条件となります。
もし何かしらの状況で未納、滞納となっている場合は、まず自治体に相談し、改善してから申請するようにしましょう。
指定されたリフォーム業者を利用すること
先ほども少し記載しましたが、自治体自治体によっては依頼するリフォーム業者が指令されている場合があります。
リフォーム業者は届出や免許が必要ないため、実績のない業者でも工事することができてしまいます。
工事を依頼するときには、自治体から指定の業者が無いかあらかじめ確認してから依頼するようにしましょう。
居住用物件のリフォームであること
助成金・補助金の対象となる建物は、居住用物件であることが条件です。
店舗や事務所として使用している建物は対象外になるため、注意しましょう。
屋根修理で助成金・補助金が支給されるケース

ここまで補助金・助成金が受けられる条件について説明をしてきました。
こちらでは、具体的にどのような工事が対象となるのか、工事のケースについて説明をしてきます。
ただし、支給条件は自治体や時期によって異なることあるためご注意ください。
太陽光パネルの設置
近年では東京都が新築住宅に太陽光パネルの設置を義務付けるなど、注目を浴びている工事です。
太陽光パネルは自然光を利用することで電力を産み出すことができるため、省エネにつながり、補助金・助成金の対象となっています。
屋根の修理とは少し異なりますが、代表的な屋根工事の一部として確認しておきましょう。
ただし、発電した電力を売却して利益をあげることを目的とした投資目的の設置は、補助金の対象外となるため注意しましょう。
屋根に断熱材を敷く
屋根の内側に断熱材を引くリフォームは、省エネリフォームとして認められることが多いです。
断熱材を敷くことで日光の侵入を軽減し、室内温度の上昇を抑えることができます。
これによって冷房等の電気の使用量が減るため、省エネにつながるとされます。
屋根の内側から断熱材を吹き付ける
断熱材を敷く方法以外にも、野地板と呼ばれる箇所に液体化されたウレタンフォームを吹き付ける断熱の方法もあります。
こちらは、断熱材を敷くのが難しい場合に、この方法が用いられることがあります。
こちらも通常の断熱材同様に、省エネ効果が期待できます。
瓦の下に断熱材を敷く
屋根の内側だけでなく、瓦の下に断熱材を敷く方法もあります。
この工事を行う際には、断熱材を敷いた後に、新しい瓦に交換する方法と既存の屋根を再利用する2種類の方法があります。
瓦屋根の修理は大きな金額が掛かるため、瓦を全部取り替える際に、一緒に断熱工事を行ってもいいかもしれません。
屋根材や屋根塗料でも断熱・遮熱効果はありますが、瓦の下にシートを敷くことで断熱効果は大きくなります。
屋根に断熱・遮熱塗料を塗る
屋根に断熱性・遮熱性の高い塗料を塗って、断熱効果を高める方法もあります。
断熱性の高い塗料は一般的な塗料と比べると高価ですが、何もしない塗料よりも省エネ効果を期待できます。
ただし、塗料の断熱・遮熱効果よりも瓦や断熱シートの方が効果は高くなります。
軽量な屋根材に変更する
屋根材を軽量化することで、家全体の耐震性を向上させることができます。
例えば瓦屋根は陶器製であるためかなり重量があり、大きな地震では倒壊してしまう可能性があります。
瓦屋根は耐震性以外の面で非常に優秀ですが、地震にはめっぽう弱い屋根材です。
これを金属製の軽い屋根材に交換することで、重量を約10分の1まで軽減できるため、耐震性が上がります。
こちらは、耐震性向上目的のリフォームとしてできますので、補助金の対象となります。
屋根修理で助成金・補助金を受け取る流れ

利用できる助成金・補助金を確認する
まずは使用できる助成金・補助金を確認しましょう。
代表的な制度としては、上記でも記載したように長期優良化リフォーム推進事業制度、省エネ改修補助事業、耐震診断・改修等補助制度の3つがあげられます。
これらは国の制度や、自治体の精度であるため、まずはどの制度が自分で使えるのかを調べてみましょう。
制度によってはすでに申請期間が終了している可能性もあるため、後回しにせずに先に調べておいた方が良いでしょう。
申請手続き
利用できる助成金・補助金があれば、申請の手続きを進めていきます。
申請書を所定の場所で入手して記入します。
また、自治体によって多少の違いはありますが、申請書の他にも以下が提出が必要です。
・外壁修理の見積書
・建物の登記事項証明書
この他にも、状況によっては追加書類を求められるケースがあります。
依頼する業者を探す
申請後、依頼する業者を探します。
自治体によっては、業者が指定されている場合があるためしっかりと確認をした上で依頼をしましょう。
また、自分で見つける場合でも助成金や補助金を使用したい旨を伝え、制度にできるだけ詳しい業者に依頼しましょう。
制度に詳しい業者であればスムーズに工事が進むため、業者選びは非常に重要です。
リフォーム前の写真撮影
業者が見つかれば、リフォーム前の写真を撮影しておきます。
自ら撮影しても問題ありませんが、屋根の上は危険であるため業者に依頼して撮影してもらうと安全です。
こちらは申請が通る唯一の証拠となるため、丁寧に撮影を行っていきましょう。
証拠が不十分であると申請が通らないこともあるため、必要以上に証拠として残しておくことは大切です。
リフォームの実施
写真の撮影が終われば、リフォームを実際に行っていきます。
こちらは、事前に業者としっかり打合せを行い、打合せ通りに工事が進んでいるかを定期的に確認していきます。
業者によっては、予定と違う工事を行い、追加料金を請求するといったケースもあるようですので、注意しておきましょう。
調査員が確認
修理が完了したら、自治体の調査員が状況を確認しに来ます。
申請通りのリフォームが実施されていた場合であれば、支給の決定通知が届きます。
実際に支給されたお金が振り込まれるのは、状況確認から1~2か月となることが多いようです。
屋根修理で助成金・補助金を受ける時の注意点

屋根修理で助成金・補助金を受け取る時には、主に5つのポイントに注意しなければいけません。
申請が通過してから業者と契約をする
助成金・補助金を申請する場合には、慌てて業者と契約してはいけません。
- リフォーム業者に相談しにいく
- 助成金・補助金を申請する
- 通過の連絡を待つ
- リフォーム工事を進める
助成金・補助金の申請が通過するのを待たずに屋根修理を進めてしまうと、万が一申請が通らなかった場合は、全額自己負担となります。
申請が必ず通るというわけではないため、通過を待ってから工事の契約をするようにしましょう。
リフォームは1社に依頼する
助成金・補助金の支給は、修理を1社が請け負った場合が対象となります。
そのため、2社にそれぞれ違う部分の修理を依頼するということはできないため、最終的に依頼する業者は一社に限定しましょう。
必要書類は事前に準備しておく
申請の際には申込書や写真の他にも必要な書類がいくつかあります。
自治体によって異なりますが、家の図面など提出も必要なケースがあり、施工業者に依頼しないと手に入らない書類があることもあります。
時間が掛かる場合もあるため、事前に必要書類をチェックしておき、あらかじめ手に入れた状態で申請するようにしましょう。
募集には期限がある
助成金・補助金の募集には期限があり、いつでも、いつまでも申し込める訳ではありません。
これは自治体の予算によって決まっているため、予算が尽きた場合は支給が早めに終了してしまうケースもあります。
4月や5月に募集を終了してしまう自治体も多いようですので、なるべく早めに申請するようにしましょう。
助成金・補助金を利用した詐欺に注意する
屋根の修理やリフォームは非常に詐欺の多い工事の一つです。
そのため、補助金を使って無料で修理ができますといった言葉で、無理やり契約を迫ってくる業者が存在しています。
補助金があるからと思って契約してしまうと、「審査に落ちてしまったので、全額払ってください。」などと詰め寄り、料金を支払わせる手口は多いようです。
このような業者がいることを忘れず、最低限の知識を身に着けた上で業者を選ぶようにしましょう。
まとめ
今回は、屋根修理の補助金制度について解説をしてきました。
あまり知られていない制度であるため、難しく感じた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、屋根の修理やリフォームは大きな金額が掛かるところですので、少しでも負担を減らすためにまずは自治体に相談してみるとよいでしょう。
申請期限があるものも多いため、まずはどの申請が使えるのか、ぜひ確認をしてください!
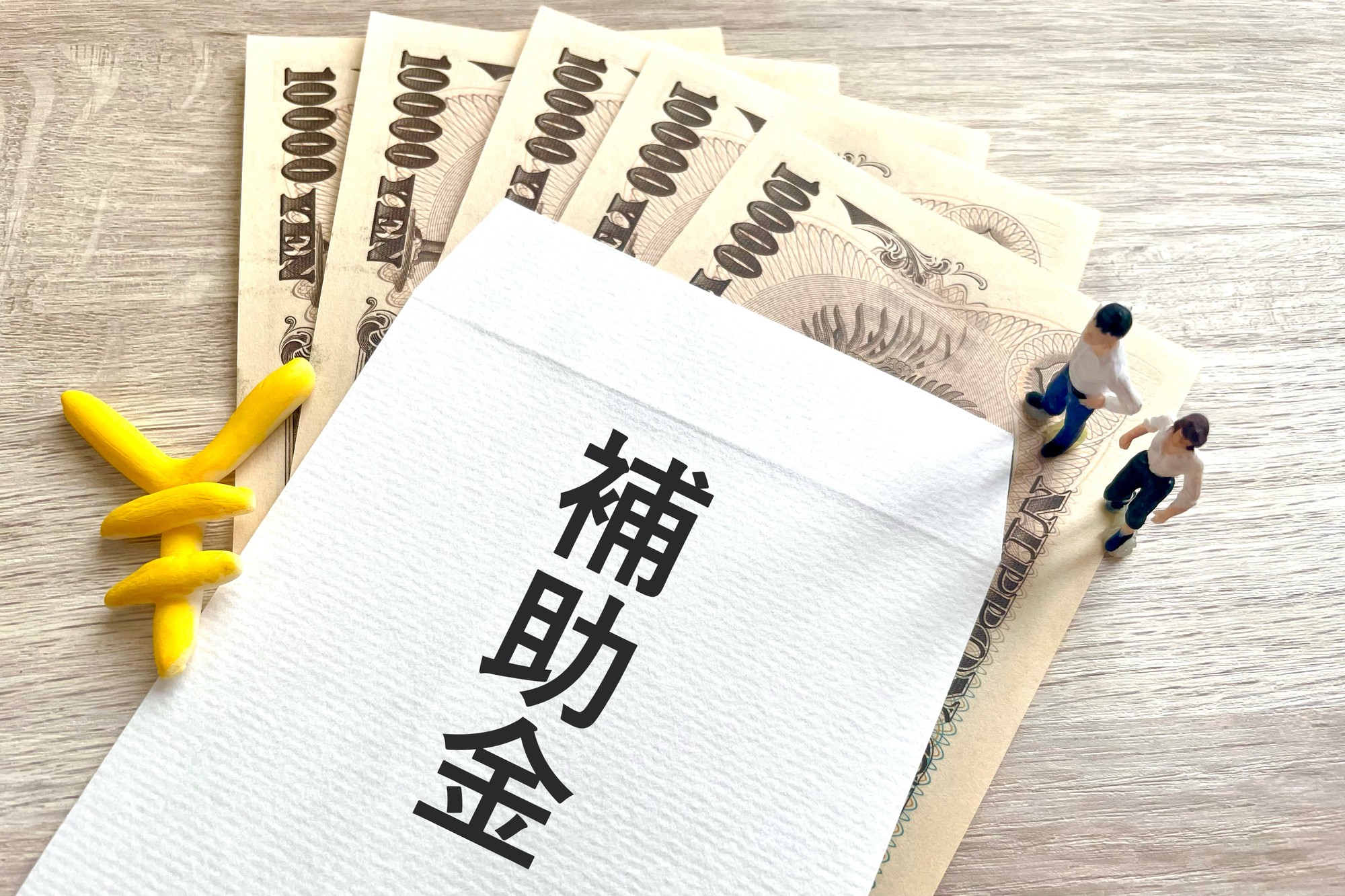










コメントを残す