屋根が壊れて応急処置が必要な時、最も手軽で効果のある応急処置方法がブルーシートでカバーする方法です。
ブルーシートでの応急処置方法を覚えておくことで、台風や大雨で雨漏りした際に自分で対応することができます。
また、雨漏りを早めに防ぐことで被害を最小限に抑え、二次災害であるシミ、カビ、シロアリなどから家を守り、ダメージを最小限にすることができます。
今回は、このブルーシートでの応急処置方法について詳しく解説をしていきます。
いつ起こるかわからない事態に備えるためにも、ブルーシートの張り方について詳しく学んでおきましょう。
Contents
ブルーシートの種類
ブルーシートにはいくつか種類がありますが、基本的にホームセンターで販売されているブルーシートを使用すれば問題ありません。
ブルーシートを選ぶ際に最も、重要視されるのが厚みです。
シートの厚さによって、防水性や強度が異なるため、なるべく厚いブルーシートを選ぶと安心です。
ただし、厚みによっては値段も変わってくるため、屋根の状態と相談しながら選ぶとよいでしょう。
おおよその値段は以下に記載します。
| 名称 | 厚み | 金額目安(3.6×5.4m)/枚 |
| 薄手(#1000) |
約0.10mm | 380円 |
| 中薄(#2000) | 約0.15mm | 790円 |
| 中厚(#2200) | 約0.17mm | 1,180円 |
| 厚手(#3000) | 約0.26mm | 1,250円 |
| 超厚手(#4000) | 約0.35mm | 1,490円 |
| 激厚手(#5000) | 約0.47mm | 1,890円 |
また、大きさに関しては、必要な幅を事前にチェックしてから決めるようにしましょう。
瓦屋根であれば、瓦一枚当たり縦25㎝、横30㎝で計算すると必要な大きさがわかります。
ブルーシートを選ぶ時の注意点

では、実際にどのブルーシートを選んだ方がよいのか、注意点について解説していきます。
ブルーシートの厚みや耐久期間
ブルーシートはまず、紫外線に強い耐性をもつものを選びましょう。
紫外線に強いブルーシートを選ぶことで、ブルーシート自体の劣化を抑えることができます。
また、厚さは3000番以上のシートをおススメしています。
3.6m×5.4mの大きさであれば、約1300円程度で購入可能です。
重さは3kgほどになりますので、多少重みを感じる程度です。
ハトメ付きを選ぶ
ハトメとは、丸いアルミ製の輪っかで、ブルーシートの四隅や端っこに付いており、ロープなどを通すことができます。
ブルーシートは土嚢を括りつけて固定するため、ハトメつきのシートを選ぶようにしましょう。
ほとんどのブルーシートには付いていますが、中には四隅しか付いていないケースもあるため、複数付いているものを選ぶようにしましょう。
ブルーシート以外に準備するもの

ブルーシートで応急処置をする際には、ブルーシート以外にも必要な道具があるため、こちらについても確認しておきましょう。
土嚢袋を用意する
まずは土嚢袋です。
土嚢簿黒は、ブルーシートの上に重しとして乗せることで、ブルーシートが風で飛ぶことを防ぎます。
土嚢袋にもUV仕様のものがあるため、そちらを選ぶとよいでしょう。
安い土嚢袋でも問題はありませんが、2~3ヶ月で破れてしまうことがあります。
屋根の上で土嚢袋が破れてしまうと、排水溝や雨どいが詰まってしまうため、なるべく頑丈なものを選びましょう。
また、土嚢袋には粗めの砂利を入れることが基本です。
細かい砂利であると、泥になって流されて、屋根を汚したり、こちらも排水溝の詰まりの原因となります。
紐を用意する
ブルーシートのハトメを通す紐選びも大切です。
紐にはたくさんの種類がありますが、丈夫でない紐を括りつけてしまうと、直ぐに切れてしまったり、外れてしまいます。
一番有効な紐は、農業用でよく利用されるマイカ線です。200mで約1,000円程度で購入できます。
マイカ線は、元々ビニールハウスで使われている紐で、紫外線や風などに強いため耐久性もしっかりとあります。
はしごを用意する
屋根に上るにははしごが必要となります。
屋根の高さに合わせて購入する必要がありますが、おおよそ6m程度のはしごを選ぶようにしましょう。
金額は1万円代のものから、5万円以上するものまであります。
なるべく安全に作業ができるように、「認証マーク付き」のはしごや、安全装置の付いたはしごを選ぶようにしましょう。
ヘルメットの用意
高所作業となるため、ヘルメットを着用しましょう。
万が一の時に守ってくれる大切な備品ですので、必ず被って作業するようにしましょう。
ブルーシートを正しく屋根に張るステップ

では、ブルーシートを正しく張るためのステップについて解説していきます。
天候に気を付ける
まずは、ブルーシートを張るためには天候に気を付けましょう。
これは安全に作業をするためには非常に重要なポイントです。
- 日差しの強い日
- 風が強い日
- 大雨の日
- 雪の日
このような天候が悪い時に作業をするのはやめましょう。
足場が悪くなり落下の危険性が高まることもあれば、体調が悪くなることもあります。
必ず安全に作業できる日を選ぶようにしましょう。
作業は二人以上で行う
まず土嚢袋等の準備が終われば、屋根に登っていきます。
その際には、必ず2人以上で作業を行うようにしましょう。
同じ屋根の斜面側に人が乗らないように棟瓦を軸に左右に分かれ、一人が重り代わりとなり、一人が作業を行います。
屋根に上がる時は、6点確保(手・膝・足)をしながら、瓦で足を滑らせないように気をつけましょう。
土嚢袋の設置方法
2つで1セットの土嚢袋を棟瓦をまたぐようにブルーシートの上に設置します。
真ん中と両端にバランス良く設置しましょう。
ブルーシートと棟瓦の間に空気が入らないように隙間を埋めることがポイントです。
その後ハトメ部分に土嚢袋の紐を通し、周りをしっかりと固定します。
風で飛ばされないかを確認
上記でブルーシートの設置は完了です。
設置した後も風で飛ばされていないか、土嚢袋がズレていないかは定期的に確認をしましょう。
屋根から落ちてきてしまうと、事故にも繋がるため、忘れずに確認しておきましょう。
ブルーシート設置での注意点
さて、ここまでブルーシートでの応急処置について説明をしてきました。
作業自体は簡単でしたが、DIYを行う上では注意点もあります。
ぜひこちらも確認をしておきましょう。
危険が伴う
最も大きなデメリットは、危険が伴う作業であることです。
屋根修理は高所作業であるため、万が一落下してしまうと大事故に繋がりかねません。
そのため、修理の際にはできる限りの安全対策を施してから作業を行いましょう。
はしごや脚立を支えてもらうために、最低2名以上で作業することや、安全靴やヘルメットなどの防具も準備できると尚よいです。
安全に作業できることが一番ですので、しっかりと注意しましょう。
補償がない
万が一DIYで失敗してしまったとしても、補償はありません。
そのため、ブルーシートを設置している途中で屋根を傷つけてしまうとまた二次災害となってしまいます。
専門業者であれば、万が一の時には補償がつきますが、自分で行った場合には補償は一切なく、時間もお金も無駄になってしまいます。
少しでも難しい作業が必要な場合は、専門業者に依頼した方が確実ですね。
屋根修理には火災保険が使えるかも?
さて、今回はブルーシートでの応急処置について解説してきましたが、屋根の修理には火災保険が適用できる場合があります。
火災保険は、火災だけでなく自然災害等で建物や家財に被害があった場合にも補償を受けることができます。
そのため、屋根修理では、火災保険が適用できる場合があります。
ただし火災保険の内容によって補償内容は異なりますので、具体的な内容については保険条項や保険会社へ確認してください。
まずは、自分が加入している火災保険を確認し、保険会社やハウスメーカーなどに問い合わせてみるとよいでしょう。
火災保険の適用条件としては、以下のような条件があげられます。
- 風災、雪災、雹災の被害であること
- 修理費用が20万円以上
- 被害発生後3年以内であること
- 屋根が契約書の保険適用対象になっていること
上記の条件を満たす場合であれば、火災保険が適用される可能性があります。
特に、屋根が火災保険の対象になっているかは、加入している火災保険の内容によって異なりますので、保障内容を確認するか保険会社に問い合わせてみましょう。
また、火災保険が適用されるかは保険会社の判断です。
保険が下りることを見越して工事をしてしまうと、適用外であった場合にすべて自己負担となってしまいます。
火災保険を使用して工事を行う場合は、必ず適用が決まってから工事を依頼するようにしましょう。
火災保険に関しては、以下の記事も参考にしてください。
⇒屋根の修理には火災保険が使える?申請方法について詳しく解説
火災保険の申請の仕方

それでは、火災保険の申請の仕方を確認していきます。
一般的な申請方法について記載していますので、実際には保険会社に相談をしながら申請を進めてみてください。
保険会社に連絡をする
まずは、加入している損害保険会社へ連絡します。
その際には、自分が加入している保険の内容や約款などを確認しながら問い合わせをするとスムーズです。
具体的には以下が確認必須の項目です。
- 補償範囲(今回のケースが該当するか)
- 免責金額(自分で負担する額)
- 保険金額の上限
- 必要書類
屋根修理の業者へ連絡をする
保険会社に連絡したのちに、修理を依頼する業者に連絡をします。
その際には、火災保険で適応したい旨を担当者に伝えることで、スムーズに手続きを進めることができます。
現地で状況を確認後、見積もりが問題なければ修理の工事をしてもらいましょう。
工事終了後に、火災保険の申請に必要な書類等を受け取ります。
修理前後の写真、見積書、請求書等が必要になります。
また、業者に依頼する際にはできる限り、相見積もりを取りましょう。
相見積もりをとった上で、しっかりと保険に対しても理解のある、信用できる業者を選びましょう。
相見積もりを取らずに工事を行ってしまった結果、トラブルになるケースも多くあるため、複数社に連絡することをおススメします。
保険会社へ申請する
修理が終われば、申請に必要な書類を記載して、保険会社へ申請します。
不備があると、保険金がすぐに受け取れない場合があるため、しっかりと内容のチェックをしましょう。
保険鑑定人の調査を受ける
申請のあと、申請内容が事実であるかどうか保険鑑定人が訪問することがあります。
これは、火災保険詐欺を防ぐためです。
申請内容とご自宅の状況に異なる点がないかなどを確認し、保険金の支給可否や金額を最終決定します。
保険金の受け取り
書類や申請内容に問題がなければ保険金が振り込まれます。
保障の内容によって全額負担、一部負担などの違いはあるため、あらかじめ保険会社と確認をしておくことが大切です。
まとめ
今回はブルーシートでの応急処置方法について詳しく解説をしてきました。
ブルーシートを敷くだけでしょうと思っている方もいらっしゃると思いますが、屋根の上の作業は非常に危険が伴います。
足場が悪いところは決して無理をせず、専門業者に依頼しましょう。
また、ブルーシートはあくまで応急処置ですので、その後はしっかりと修理業者に根本の修理を依頼するようにしましょう。





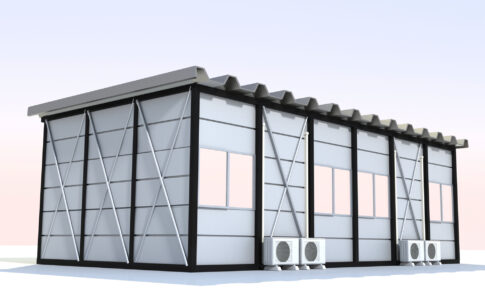


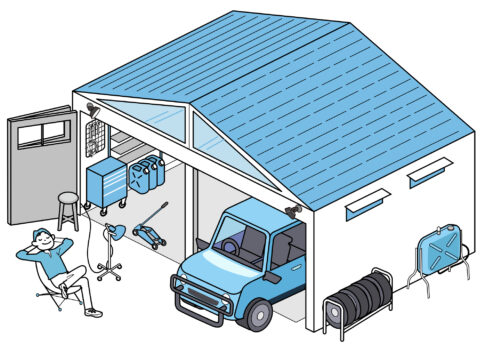


コメントを残す