突然発生する雨漏りは、どのような建物でも起きうる可能性があります。
その中で今回は、ビルで雨漏りが起きた時の対処方法について解説をしていきます。
仕事中突然雨漏りがしてくるといった可能性も十分に考えられるため、落ち着いて行動できるようにしましょう。
Contents
ビルで雨漏りする原因について

まず、ビルで雨漏りする原因について解説をしていきます。
大きく分けると4つの原因があるため、それぞれについて見ていきましょう。
屋上の排水不備
ビルの屋上は、平らな構造となっている「陸屋根」が使用されているケースがほとんどです。
陸屋根は、水はけのために傾斜をつけて設計・建築するのが一般的ですが、場合によっては水が溜まってしまうこともあります。
例えば、排水溝に落ち葉やゴミが詰まり、屋上に水が溜まるケースが考えられます。
屋上部分は、防水加工はされていますが、風雨や外気によって経年劣化が進み、表面が徐々に劣化していきます。
最終的に子の劣化部分から雨水がしみこみ、雨漏りの原因となっていきます。
外壁の劣化
ビルの外壁は、コンクリート部分とコーキング部分が劣化していきます。
鉄筋コンクリートで建てられているビルはコンクリートと、コンクリートのひび割れ防止をするためにコーキング材が使用されています。
このコンクリートやコーキング材は、雨風や紫外線等に長年当たっていると、経年劣化し、ひび割れが起きてきます。
子のひび割れが大きくなると、コンクリートの内部に雨水が侵入し、雨漏りや建物の耐久性を低下させる原因となります。
鉄筋コンクリートの場合は、内部の鉄筋部分がサビてしまう可能性があるため、外壁のヒビは注意すべきポイントです。
窓の劣化・施工不良
窓からの雨漏りも多い事象です。
原因としては、サッシの歪みやコーキング材の劣化などが考えられます。
また、サッシの水切り施工不良や、パッキン不良などが原因になるケースもあります。
これらは対象部位の経年劣化によって引き起こされることもありますが、中には施工不良や、製品自体の不良品といった可能性も考えられます。
特に修理した直後や工事後直ぐに起きた場合は、施工不良の可能性が考えられます。
直ぐに担当業者に連絡をして、確認をしましょう。
ビル内部の配管破損
雨漏りとは少し異なりますが、ビル内での水漏れも起こりうる事故です。
ビルの内部には、給水管・給湯管・排水管・エアコンのドレーン管など、様々な配管があります。
その配管は経年劣化や何かしらの原因で、破損したり、詰まったりすることがあります。
特に、給水管や給湯管など、常に水圧がかかってる配管は注意が必要です。
給水管や給湯管が破損が破裂してしまうと、元栓を締めるまでお湯や水が止まりません。
さらに、汚水管の破裂となると、悪習などが広がってしまいます。
こちらは日常的に予防をすることは難しいですが、しっかりとメンテナンスを定期的に行うことが大切となります。
ビルで雨漏りが発生した時の行動

ではビルで雨漏りを見つけた時にどのような行動をとればいいのでしょうか。
普段ビルにあるオフィスで働いている方は、仕事中に急に雨漏りが発生したとイメージして考えてみてください。
普段なかなか起きないことですので、慌ててしまうこともあると思いますが、初期対応をしっかりとすることで被害の拡大を抑えることができます。
応急処置を行う
まずは応急処置を行う準備をしましょう。
雨漏りの発見は、天井や壁から水が滴り落ちてくるところから発見されることが多いと思います。
雨漏りを見つけたら、まずはバケツと雑巾等の確保です。
バケツや雑巾を使って、落ちてくる雨水をしっかり受け止めましょう。
これによって、床への被害拡大を抑えることができます。
また、電子機器などが近くにある場合は、コンセントを抜いておきましょう。
万が一の漏電や機械の故障を防ぐことができます。
管理会社に連絡する
応急処置が終わった後は、ビルの管理会社に連絡をしてください。
自社ビルであれば、業者への依頼等は自社で行いますが、賃貸契約の場合は管理会社に連絡する必要があります。
管理会社に依頼をして、業者の手配や他の入居者へのお知らせを行ってもらいましょう。
勝手に修理業者を手配してしまうと、管理会社との契約上の問題が出てしまう可能性も考えられるため、まずは管理会社に問い合わせた方が安全です。
もしも緊急性を要するものであれば、業者を手配したい旨を管理会社に伝えてください。
記録をとっておく
応急処置と管理会社への連絡の後は、雨漏りの記録をしっかりととっておきましょう。
写真や動画を使って、映像で残すことをおススメします。
これは、修理業者が修理箇所を特定するための大きな助けとなります。
また、火災保険等を使用する際にも使える証跡となるため、記録に残しておくことをおススメします。
雨漏りはビルの耐久性を低下させる
ここまで、ビルで雨漏りが起こった際の対処方法について解説をしてきました。
しかし、「多少の雨漏りであればそこまで気にすることも無いのではないか?」
「ビルはコンクリートだし、わざわざ工事しなくても大丈夫だろう。」
このように考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、雨漏りはビルのコンクリートでさえも耐久性を下げてしまう可能性があります。
その内容について見ていきましょう。
ビルは鉄とコンクリートで作られている
イメージしやすいとは思いますが、ビルはコンクリートとその中に鉄骨が入っている、鉄筋コンクリートで作られています。
これは、耐久性をあげるために工夫されたものですが、実はこの鉄に不具合があると大惨事になってしまう可能性があります。
サビがコンクリートの壁を破壊する?
鉄であるため、水に濡れると当然サビが発生します。
サビだけであればそこまで問題ないと考えるかもしれませんが、このサビが広がっていくと徐々に脆くなり耐久性が無くなります。
そしてさらに、爆裂と呼ばれる現象に繋がります。
鉄はサビていくと、酸素が付着して体積が増えていきます。
体積が増えると、周りのコンクリートも膨張していき、これに耐えられなくなったコンクリートが割れてしまいます。
この事象は珍しくなく、突然割れたコンクリートが人にぶつかってしまいケガをするという事故は何件も起こっています。
この現象も危険ですが、コンクリートが割れてしまうことで元の建物の耐久性も下がっていきます。
雨漏り対策が重要!
これらの事象は雨漏りやヒビから侵入した水分が原因で引き起こされています。
そのため、雨漏りくらい大丈夫とは思わずに、直ぐに対策を行いましょう。
先延ばしにしてしまうと、手が付けられなくなる可能性もあるため、なるべく早急な対応が必要となります。
ビルの雨漏り原因の特定方法

ビルは建物が大きい分、雨漏りの原因を特定するのが大変です。
そこで、こちらでは主にビルでの雨漏りの原因を特定する手法についていくつか紹介をしていきます。
目視調査
まずは、最も手軽な目視調査です。
室内の漏水状況や外部のひび割れなどを、目で確認する方法です。
本格的な調査の前に、おおよその見当をつけます。
見当を付けておくことで、調査個所を限定し、コスト削減にもつながるため、かなり有効な調査方法です。
散水調査
散水調査は、雨が降っているのと同じ状況を再現して、雨漏りの状態を確認します。
目視調査で見当をつけた場所に水を流し、その水が雨漏りとなっているのかを確認します。
目視調査とセットで行われることが多い調査です。
紫外線投射発光検査
紫外線投射発光検査は、雨漏りが複数箇所ある場合に使用します。
雨漏りの原因と見当をつけた場所に、ブラックライトに当たると発光する特殊な液を散水し、7色の検査液を使い分けて、雨水の侵入経路と漏水箇所の因果関係を調べます。
有用な手段ではありますが、検査薬で変色してしまう素材もあるため、使用出来ないケースもあります。
電気抵抗試験
コンクリートが通電しない性質を利用するのが、電気抵抗試験です。
コンクリートのひび割れ部分に水が入り込むと、電気を通す物質が発生します。
その物質が生じると、電気抵抗値に変化があるため、原因箇所を特定できる仕組みです。
赤外線調査
赤外線調査は、高感度の赤外線カメラを使用して、建物の温度差から雨漏りの原因箇所を特定します。
水を含んだコンクリートは温度が低下するため、その温度を調べることで原因が特定できる仕組みです。
スピーディに原因の特定ができますが、調査費用が高額になることが多く、日当たりなどの環境によっては調査できない場所もあります。
ガス調査
ガス調査は、漏水箇所から特殊なガスを放出することで、ガスが出てくる場所を特定します。
建物全体を一斉に調査する時に適した調査方法で、まだ雨漏りまでは進行していない箇所の特定も可能です。
ただし、正確な原因特定が出来ないケースがあるため、建物全体の予防的な意味合いで調査するときにおススメです。
打診調査
打診調査は、外壁や屋根部分を専用の器具で叩いて原因箇所を特定します。
これは、外壁の強度などを測るときにも用いられる方法です。
作業員が一つ一つ確認をしていくため、時間はかかりますが、近年は安全に調査できるようになったこともあり、今注目を浴びている調査方法の1つです。
まとめ
今回はビルで雨漏りが発生した時の対処法について詳しく解説をしてきました。
まず、雨漏りを見つけた際には、応急処置をして管理会社に連絡を直ぐにすることを徹底しましょう。
これだけでも被害を最小限に抑えることができ、仕事や生活への支障が少なくなります。
頑丈なつくりであっても、いつ雨漏りが起こるかは予想がつきません。
ぜひ、この機会に対応方法について確認をしておきましょう!








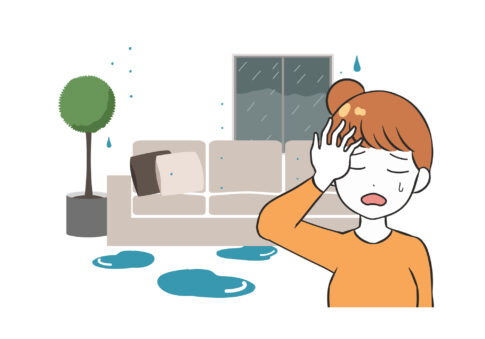


コメントを残す