積雪の多い地域では、雪による雪害に悩まされることがあります。
その中でも、屋根に雪が積もりその重みで屋根が損傷してしまったり、雨どいが損傷してしまったりと、屋根に関するトラブルは多く見受けられます。
自然災害ですから、なかなか対策をしっかりしておいても、対応しきれない場合は出てきてしまいます。
今回は、雪害によって屋根が被害を受けてしまったときの修理方法を中心に解説をしていきます。
特に積雪の多い地域の方は、参考にしてみてください。
Contents
屋根が雪害を受けないようにするには?

まず、屋根の雪害を防ぐためにはどうすれば良いのでしょうか。
こちらは多くの家庭でされているとは思いますが、一番は屋根からの雪下ろしを徹底することです。
雪は水分を含んでいるとかなりの重量になります。
そのため、多くの雪が屋根に積もるとその重みで屋根が損傷してしまいます。
特に屋根の角度が低い家や屋根が平らな家は、雪が積もりやすく負担がかかりやすいです。
寒い中かなり負担の掛かる作業ではありますが、屋根が潰れて家全体に被害が及ぶことないためにも、雪下ろしは行っていきましょう。
積雪が多い場合は、危険な作業となるため、充分に注意して行ってください。
雪害による屋根の被害について

では、実際に大雪によって屋根が受ける被害について詳しく見ていきましょう。
屋根の破損
雪害で最も多く報告されるのが、屋根の破損です。
具体的には、雪の重みで屋根材が割れてしまったり、瓦が割れる、雨どいが壊れるといった損傷が多く見受けられます。
これは、雪の重みに屋根材や雨どいが耐えられなくなって起こることです。
また凍害と呼ばれる現象も屋根材のひび割れの原因となります。
屋根材や雨どいが破損してしまった場合は、部分的に交換する必要があります。
瓦屋根
屋根材が瓦屋根であれば、破損した部分だけを取り替えることができるため、比較的修理も簡単、少額で済ませることができます。
瓦は特殊なものでなければ、形が全国で共通している形が出回っているため、差し替えする際も比較的簡単に工事を行うことができます。
金属屋根
屋根材が金属屋根の場合、基本的には瓦屋根と同じように部分的に交換することが可能です。ただし、金属屋根は近年材質が変化し、ガルバリウム鋼板が主流となりました。
ガルバリウム鋼板以外の金属を多く扱っている業者が少なくなってきたこともあり、同じ材質の屋根材を探すのが難しくなっているようです。
雨どい
雨どいの修理についても、樋の材質や形状が近年の住宅洋風化によって変化しているようです。そのため、既存のものとまったく同じ形にはできない可能性があります。
ただし、もっとも一般的な半円の雨どいであれば、ほとんどのメーカーで扱っているため、問題なく交換することができます。
部分修理ができない場合
さて、ここまでは瓦屋根や金属屋根については部分修理ができると記載してきました。
ただし、同じ種類の屋根材が無い場合は、屋根全体を交換せざるを得ない可能性があります。
また、ただ屋根材が故障しているだけでなく、屋根の下の土台に被害が出ている場合もあります。
このような場合は、屋根を取り換えるだけでなく、さらに修復が必要となります。
一部だけ屋根材が異なると、綺麗に修復ができず、また破損や雨漏りの原因になってしまう可能性があるため、屋根全体の状態によっては全面葺き替えの可能性があることも考えておきましょう。
葺き替えには、屋根の上に屋根材を載せるカバー工法と屋根を取り換える葺き替えの二種類があります。こちらは後述しますが、葺き替えよりリーズナブルなカバー工法で済むことが多いようです。
長く生活を支えてくれる場所ですので、雪害の際にはまず修理業者に連絡して点検してもらうことをおススメします。
屋根が曲がってしまった
屋根は破損してはいないけれども、屋根全体が曲がっている、歪んでいるといったケースも雪害には多い被害です。
これは、屋根材自体は雪の負担に耐えられても、家の柱や梁(はり)と呼ばれる家を支える部材が劣化して、雪の重さに耐えられなくなっている状態が多いです。
この場合は、屋根材ではなく家の骨組みが劣化していることが問題です。
そのため、屋根材を変えるだけでは充分に補強することができず、躯体と呼ばれる柱や梁自体の補強や、屋根を支える束や垂木の取り換えなどが必要となります。
大がかりな工事となるため、屋根修理業者や工務店、大工さんに相談してみましょう。
大雪での雨漏り(凍害、すがもり)

大雪では屋根が破損する以外にも、雨漏りが発生してしまう被害があります。
雨漏りが発生する原因としては、上記で記載したように屋根が破損し、そこから雨水が侵入して雨漏りとなってしまうケースがまず考えられます。
そして、これ以外にも凍害やすがもりといった原因が考えられます。
凍害とは
まず凍害とは、屋根材の中に水分が入り、その水分が凍ることで体積が大きくなる凍結膨張が発生します。この氷が溶けると膨張した部分は元に戻らず、またそこに水が溜まって膨張して、溶けてを繰り返すことで、徐々に屋根材の材料が徐々に劣化することです。
氷点下になるような地域では多く見られ、コンクリートなどでもよく見られる現象の1つです。
凍害を防ぐには、その地域に適した屋根材を選択することが最も効果的です。
一般的には、水をあまり含まない含水率が低い瓦や、水を吸収しない金属屋根が良いとされています。
瓦は地域によって特徴があるため、瓦屋根を検討している方は、業者に確認してみるといいかもしれません。
すがもりとは
すがもりも雨漏りの原因となる現象です。
すがもりは屋根に積もった雪が紫外線によって溶けて水となり、屋根材のすき間をぬって室内に浸入する現象です。
通常であれば水は流れていくため、屋根材の隙間に侵入することはありませんが、軒先につららができると水の流れがせき止められ、屋根の上に水が溜まってそこから室内に侵入します。
すがもれは屋根に積もった雪が溶けて生じる現象なので、雪の多い地方では浸透している言葉です。「すが」は東北地方の方言で「氷」を意味します。つまり、氷や雪が屋根に積もり、それが原因で発生する水漏れを「すがもり」と言います。
すがもりのメカニズムについては、以下を確認してください。
- 屋根に積雪する
- 屋内の暖房の熱が屋根に伝わり、積もった雪が溶ける
- 溶けた雪が水となって屋根の上を伝い、軒から落ちる
- その一部がつららになる
- つららが出来ることによって、軒付近の水の通り道が塞がる
- 行き場のなくなった水が屋根の上に停滞する
- 水がどんどん溜まって、屋根のつなぎ目から侵入し室内に漏れる
すがもりの対策方法は、屋根の雪を家の熱で溶かさないことが対策となります。
- 屋根の天井面に断熱材料を施工する
- 天井に断熱材料を施工したうえで、屋根裏を換気する
- 軒先部分を加熱することでつららの発生を防止する
- 屋根の勾配を急にして雪が溜まらないようにする
このように、すがもりの対策はつららを作らないことが大事になるため、断熱材で対処を行ったり、雪下ろしと同時につららも撤去するといった対策が重要となります。
屋根の修理費用の目安

では、実際に屋根の部分修理や葺き替え、雨漏りの修理費用について確認していきます。
費用は屋根の大きさや足場などによっても大きく変わるため、あくまで参考値としてください。
実際には複数社にきちんと見積もりをとった上で、工事を依頼するようにしましょう。
部分修理の費用相場
| 工事内容 | 工事相場 |
| 屋根の差し替え | 4万~20万円 |
| 棟板金の交換 | 4万~15万円 |
| 漆喰の補修 | 3万~10万円 |
| 部分的な瓦の交換 |
3千~5万円 |
| 棟瓦の積み直し | 4万~15万円 |
| 谷樋板金の交換 | 5万~20万円 |
| 雨どいの部分補修 | 2万~8万円 |
| 雨どいの全部交換 | 18万~30万円 |
| 雪止めの設置 | 3万~50万円 |
| 雨漏りの補修 | 5万~30万円 |
リフォームの費用相場
| 工事内容 | 工事相場 |
| 雪止めの交換、設置 |
10万~30万円 |
| 屋根塗装 | 15万~25万円 |
| 屋根カバー工法 | 90万~110万円 |
| 屋根葺き替え | 100万~140万円 |
| 屋根葺き替え(石綿入り) | 130万~170万円 |
| 屋根葺き替え(土葺き) | 160万~200万円 |
屋根修理には火災保険が使えるかも?
火災保険は、火災だけでなく自然災害等で建物や家財に被害があった場合にも補償を受けることができます。そのため、屋根修理では、火災保険が適用できる場合があります。
ただし火災保険の内容によって補償内容は異なりますので、具体的な内容については保険条項や保険会社へ確認してください。
まずは、自分が加入している火災保険を確認し、保険会社やハウスメーカーなどに問い合わせてみるとよいでしょう。
火災保険の適用条件としては、以下のような条件があげられます。
- 風災、雪災、雹災の被害であること
- 修理費用が20万円以上
- 被害発生後3年以内であること
- 屋根が契約書の保険適用対象になっていること
上記の条件を満たす場合であれば、火災保険が適用される可能性があります。
特に、屋根が火災保険の対象になっているかは、加入している火災保険の内容によって異なりますので、保障内容を確認するか保険会社に問い合わせてみましょう。
また、火災保険が適用されるかは保険会社の判断です。
保険が下りることを見越して工事をしてしまうと、適用外であった場合にすべて自己負担となってしまいます。
火災保険を使用して工事を行う場合は、必ず適用が決まってから工事を依頼するようにしましょう。
火災保険に関しては、以下の記事も参考にしてください。
⇒屋根の修理には火災保険が使える?申請方法について詳しく解説
火災保険の申請の仕方

それでは、火災保険の申請の仕方を確認していきます。
一般的な申請方法について記載していますので、実際には保険会社に相談をしながら申請を進めてみてください。
保険会社に連絡をする
まずは、加入している損害保険会社へ連絡します。
その際には、自分が加入している保険の内容や約款などを確認しながら問い合わせをするとスムーズです。
具体的には以下が確認必須の項目です。
- 補償範囲(今回のケースが該当するか)
- 免責金額(自分で負担する額)
- 保険金額の上限
- 必要書類
屋根修理の業者へ連絡をする
保険会社に連絡したのちに、修理を依頼する業者に連絡をします。
その際には、火災保険で適応したい旨を担当者に伝えることで、スムーズに手続きを進めることができます。
現地で状況を確認後、見積もりが問題なければ修理の工事をしてもらいましょう。
工事終了後に、火災保険の申請に必要な書類等を受け取ります。
修理前後の写真、見積書、請求書等が必要になります。
また、業者に依頼する際にはできる限り、相見積もりを取りましょう。
相見積もりをとった上で、しっかりと保険に対しても理解のある、信用できる業者を選びましょう。
相見積もりを取らずに工事を行ってしまった結果、トラブルになるケースも多くあるため、複数社に連絡することをおススメします。
保険会社へ申請する
修理が終われば、申請に必要な書類を記載して、保険会社へ申請します。
不備があると、保険金がすぐに受け取れない場合があるため、しっかりと内容のチェックをしましょう。
保険鑑定人の調査を受ける
申請のあと、申請内容が事実であるかどうか保険鑑定人が訪問することがあります。
これは、火災保険詐欺を防ぐためです。
申請内容とご自宅の状況に異なる点がないかなどを確認し、保険金の支給可否や金額を最終決定します。
保険金の受け取り
書類や申請内容に問題がなければ保険金が振り込まれます。
保障の内容によって全額負担、一部負担などの違いはあるため、あらかじめ保険会社と確認をしておくことが大切です。
まとめ
今回は、雪で屋根が被害を受けた時の対応方法や修理に掛かる金額について解説をしてきました。
積雪地域では、毎年のように雪害に悩まされているとことも多いと思います。
特に雪害の影響を受けやすいところは屋根の上ですので、これを機会にどのような被害があるのか、どれくらいの費用が掛かるのかは抑えておきましょう。
不安な点があれば、ぜひ専門業者に連絡してみてくださいね。










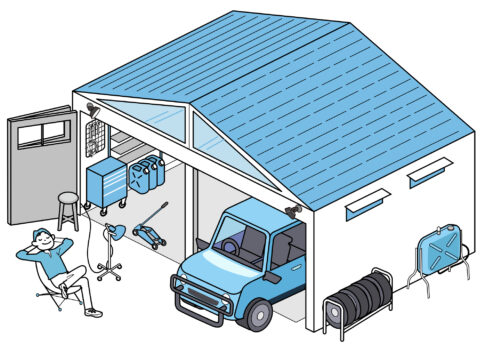
コメントを残す